こんにちは!うしたろう不動産のうしたろうです!
不動産業界経験20年以上の私が不動産投資の基本をお伝えします。
今回は不動産投資を始める上で最初に押さえておくべき重要事項、「減価償却」について解説します。
今回は不動産投資の入門編ですので不動産に関わる「減価償却」について話を進めます。
眠くなりやすい話題ですが、賃貸不動産をしっかりと経営していく上でとても重要なポイントですので頑張って最後までお付き合いください!
減価償却償却とは
基本
減価償却とは、不動産である建物や設備が年月の経過により劣化していき、収益不動産としての建物・設備の価値を減らしていくことを税法上、反映させていく仕組みです。
減価償却は税法上の考え方
あくまで税法上です!実際の老朽化とは違います。建物の場合、躯体構造に応じて年数が決まっていますが、その年数に経ったから朽ちて使用できなくなる?と言うものではありません。
何度も言います!税法上です!
土地部分はどうなるの?
土地は建物と違って年数によって老朽化しませんので、減価償却の考え方はありません。経費化は出来ないと言うことです。
どんなふうに税法上反映されるの?
建物や付属する設備を取得した際にかかった費用を一括で損金処理はできません。
取得税・住民税の下記のように課税されます。
売上➖経費➖控除=課税所得
この課税所得に税率をかけて計算します。
と言うことは経費を多く計上できれば課税所得が低くなり、支払う税金も安くなると言うことですね。
実際のお金の動き(キャッシュフロー:CF)とは異なる点がポイントです!
不動産などの大きな金額の場合、一度に経費として計上すると所得がなくなるので税金がなくなりますね。
それでは国の税収がなくなり困ってしまいます。
また、給与や役員賞与などの所得が多い人が所得調整を目的に不動産を購入して税金を払わないようにしてしまうことも出来てしまいます。
そうならない様に、建物などのように多額なものは一度に経費化するのではなく各年度で分割して経費を損金計上してください、と言うのが「減価償却」の基本的な考え方です。
構造によって分割する期間が決まっています。
下記の通り構造によって期間が決まっています。主なものを紹介します。
鉄筋コンクリート造 47年
鉄骨造 19年・27年・34年(鉄骨の厚みによる、3段階)
木造 22年
設備:電気、ガス、給排水設備、フェンスやブロックなどは15年
エアコン、冷暖房機器などは6年
中古で取得した場合などのその他ルール
中古で取得した場合の耐用年数は?
中古で取得した場合は(残存期間+経過年数の2割)となり、少し耐用年数が復活します。
具体的な計算方法
計算式=(上記の法定耐用年数➖経過年数)➕(経過年数✖️20%)※小数点以下切り捨て
個人と法人の違い
個人も法人も同じく「定額法」といって年数で均等割で経費化します。
以前は「定率法」と言って最初に多く、終盤になるほど少なくという方法が選択できましたが、今はできません。
法人の場合の特典として、その年に償却(経費計上)するかどうかを法人が選択することが出来ます。
調整できると言うことですね。法人についての詳細はまたの機会に。
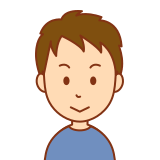
今回は不動産投資で最初に押さえておくべきポイント!
【減価償却】の基礎の基礎をお伝えしました。
この部分は不動産経営において避けることのできない重要なポイントです。
タックスコントロールですね!



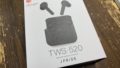

コメント